
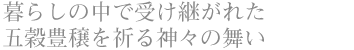
高千穂峡からほど近い「高千穂神社」で毎夜20時から行われる観光夜神楽。静かな神楽殿に笛と太鼓の荘厳な音色が響きます。高く、低く、まるで足音が近づいてくるようなお囃子に合わせ、“奉仕者(ほしゃ)どん”と呼ばれる舞い手が現れる。“おもてさま”と呼ばれる面で人々を見据えると、まるで表情さえ変わって見えます。それは“奉仕者どん”が“神”となった瞬間。天の岩戸隠れにちなんだ「手力雄(たぢからお)」などの神楽を鑑賞しながら、神々の時代へと思いを馳せるのもいいものです。
毎年11月末~2月上旬には各集落の神楽宿で、夕方から翌日の昼まで全三十三番が夜通し舞い続けられます。高千穂で暮らす誰もが神楽に関わる“伝統の守り手”なのです。



(上) 「御神体の舞」は“国生みの舞”や“酒こしの舞”ともいわれ、伊邪那岐命(いざなぎのみこと)と伊邪那美命(いざなみのみこと)の夫婦円満を象徴する舞だ
(左) 神楽面は、高千穂町の伝統工芸。一つ一つ手作業で彫っていく。地元では家の軒先に魔よけの神楽面を飾る風習もあり、まさに神楽の里という風情に満ちている

観光神楽が奉納される高千穂神社は、1200年もの歴史を誇る高千穂八十八社の総社にあたる。男女手を繋いで夫婦杉の周囲を3周すると家内安全・子孫繁栄など願いが叶うとか






